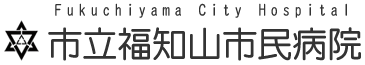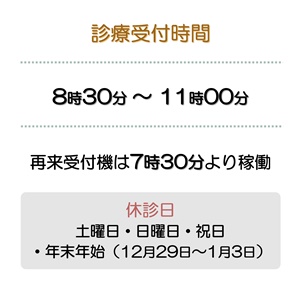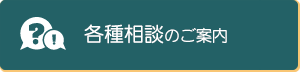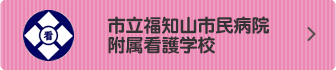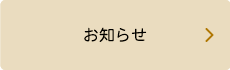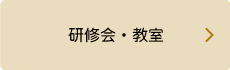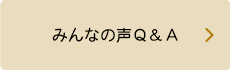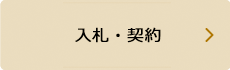本文
循環器内科
*知りたい内容をクリックしてください。
特色 / 診療内容 / 治療成績 / 今後の方針 / 学会学術活動 / 週間診療予定表 / 担当医師
レセプト及びDPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する研究 [PDFファイル/10KB]
特色
当科は急性心筋梗塞に代表される緊急性を要する循環器疾患を専門に扱う科です。福知山市76,000人に加え、中丹医療圏(福知山市、綾部市、舞鶴市の20万人弱)、隣接する丹波医療圏(丹波市、篠山市の約10万人)、但馬医療圏の南部(朝来市、養父市、豊岡市の南部地域)を含めた広いエリアで循環器緊急を受け入れる病院が不足している現状で、これらの隣接地域からの救急搬入も積極的に受け入れており、ドクターヘリ搬送も年間数件受け入れています。
また、高齢化に伴い全身状態悪化の終末像としての心不全の発症及び再発が全国的に増加の一途を辿っており、当該医療圏も同様です。高齢化率30.6%は全国平均28.8%を超えています。慢性心不全は増悪と緩解を繰り返しながら次第にADLを低下させ、最終的に末期を迎える疾患です。現在本邦の死亡率第2位を占める心疾患(全死亡の14.9%)のうち、心不全が最多(41%)を占めており、心不全末期の患者におけるQOLサポートとしての心不全緩和ケアの需要が増しています。当施設は総合内科が充実しており、当科と総合内科が連携を図り、患者および家族のニーズに合わせて主科を割り振り、2つの科で心不全診療に当たっている特色があります。
更に、高齢化と動脈硬化性疾患の増加に伴い下肢閉塞性動脈硬化症も増加しています。同疾患は歩行機能障害を引き起こし、QOLの低下のみならず種々の生活習慣病の悪化を引き起こす元凶になり得る疾患です。当施設では、カテーテル検査の際に全身の動脈硬化のスクリーニングを積極的に行い早期診断と治療を心掛けています。
診療内容
当院は日本循環器学会指定、循環器研修施設に認定されています。また、2018年8月からは新たに日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設に認定されました。循環器内科で365日オンコール体制を引き、救急疾患は全例お受けするようにしています。緊急性の高い急性心筋梗塞, 不安定狭心症, 重症虚血肢, 急性動脈閉塞症, 急性肺塞栓症などにおいては積極的にカテーテル診断・治療を行い、不整脈疾患に関してはペースメーカー治療を行っています。2022年4月からは大学から招聘医師をお招きし、不整脈疾患に対するカテーテルアブレーション治療も始めました。その他, 急性心不全, 慢性心不全急性増悪, 不整脈疾患、弁膜症, 心筋変性疾患, 高血圧性心疾患, 先天性心疾患, 大動脈疾患, 肺高血圧症, 静脈疾患, 腎動脈疾患など多岐にわたる循環器疾患に対しても可能な限り積極的に治療に取り組んでいます。また、地域の先生方からご紹介頂いた症例に関しては、極力詳細な診療情報を記載し、心不全に至った要因や、再発予防のポイント、今後の診療の重点をお伝えするよう心掛けています。
治療成績
当院の診療実績は別表に示す通りです。虚血性心疾患の診断に関しては症例に応じて冠血流予備量比(FFR, iFR, RFR)を測定し、適正な心臓カテーテル治療(PCI)を実施するよう心掛けています。PCIではほぼ全例に血管内超音波(IVUS)もしくはIVUSの約10倍の解像度を有する光干渉断層診断(OFDI)を使用し、より詳細なプラーク性状の質的診断を得ることにも努めています。また、2021年6月からは高度石灰化病変に対してRotablator TMによる石灰切削治療も導入しました。また、2021年9月には血管撮影装置(Philips社製Azurion)を刷新し、患者様の被爆低減とより明瞭な画像診断に努めています。また、2023年4月からは冠微小冠循環障害(MCD)を評価できる最新の診断ツールCoroFlow TMを京都府北部でいち早く導入しました。従来、非閉塞性冠動脈病変(INOCA)の臨床診断が不十分で、心外膜レベルの冠動脈に有意狭窄病変がなく冠攣縮誘発試験も陰性で胸痛の原因が分からなかった患者様を含めて、より正確に包括的な冠動脈疾患の評価が可能になるものと期待しています。
また当院は2009年4月より京都府北部の医療機関で最も早く包括的心臓リハビリテーションを導入していています。心筋梗塞、狭心症、心不全、閉塞性動脈硬化症等の患者様にカテーテル治療、薬物療法だけでなく、運動療法、栄養指導、禁煙指導、生活習慣指導等を実施するものです。心臓に負担とならない運動強度を評価するための心肺運動負荷試験(CPX)を実施し、適切な運動指導を実施しています。急性期を脱した早期から離床訓練を開始し、積極的な運動療法で心肺機能と体幹の筋力を回復させ、社会復帰して頂くことに貢献しています。また包括的心臓リハビリテーションは定期外来と比し密に患者に受診頂くことで体調変化にきめ細かな介入を行うことが可能で、心臓だけでなく全身の機能低下に対する治療に繋がる他、患者様の意識・行動変容にも繋げるきっかけになり、心不全患者の治療の大きな柱になっていると考えています。
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経皮的冠動脈形成術(PCI) | 214 | 217 | 208 | 253 | 228 |
| うち緊急経皮的冠動脈形成術 (E-PCI) |
48 | 67 | 52 | 75 | 74 |
| 経皮的末梢血管形成術(EVT) | 92 | 127 | 122 | 135 | 101 |
| ペースメーカー移植術(PMI) | 20 | 25 | 35 | 38 | 22 |
| 外来心臓リハビリテーション | 1,791 | 1,695 | 1,161 | 1,257 | 1,174 |
| 入院心臓リハビリテーション | 2,585 | 2,525 | 3,021 | 2,793 | 2,754 |
今後の方針
京都北部にあっても都市部の治療レベルと遜色のない最善の医療を患者様に提供し、患者様に満足して頂ける地域完結型の診療体制を構築することを目標としています。カテーテル治療はデバイスの進歩により低侵襲で便利な治療法として日本全国に拡がり、当院のような一地方施設でも広く施行可能な治療になりました。が、動脈硬化を来した心臓の血管を遠隔で操作する点で危険な治療法であることには変わりなく、時に生命に関わる合併症を孕むことは事実です。極力合併症を避けるべく患者様一人一人の病態を把握し、細心の注意を払って診療に当たってゆきます。
近年Structure heart disease(SHD)の分野に関して、本邦でも超高齢者に対応した、より低侵襲な治療法が目白押しで登場しつつあり、まさに日進月歩の感があります。この新時代に地方でも遅れることなく柔軟に対応し、京阪神全体の心臓血管外科施設と連携をとり、最善の治療を受けて頂けるよう、地域の中核病院としての職責を果たしてゆく所存です。
日々の診療レベルと実績を上げる努力を怠らないことで魅力ある施設にし、若手医師の集まる活気のある施設を目指します。また、地域の先生方とより積極的な交流を図り、今後益々増え続ける心不全診療に、より風通しの良い地域医療を提供することを目指します。
学会学術活動
日本循環器学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本不整脈心電学会、日本心臓病学会、日本心臓リハビリテーション学会、その他
担当医師
| カンバヤシ ダイスケ 上林 大輔 (副診療部長 兼循環器内科医長) |
最終学歴 | 京都府立医科大学 平成9年卒業 |
|---|---|---|
| 専門分野 | 循環器一般、心血管疾患のカテーテル治療 | |
| 専門医・認定医等 | 京都府立医科大学臨床教授 日本循環器学会認定循環器専門医 日本内科学会認定医 日本心血管インターベンション治療学会専門医 日本心臓リハビリテーション学会認定 心臓リハビリテーション指導士 |
|
| サカモト タカシ 阪本 貴 (循環器内科医長 兼地域医療連携室長) |
最終学歴 | 京都府立医科大学 平成8年卒業 |
| 専門分野 | 循環器一般、不整脈 | |
| 専門医・認定医等 | 日本循環器学会認定循環器専門医 日本内科学会認定医 |
|
| マツバラ ユウキ 松原 勇樹 (循環器内科医師) |
最終学歴 | 大阪医科大学 平成27年卒業 |
| 専門分野 | 循環器内科 | |
| 専門医・認定医等 | 日本循環器学会認定循環器専門医 日本内科学会内科認定医 心血管インターベンション認定医 |
|
| 診療についてのモットー | いつも笑顔で自分にできる事を100%出し切ります。 | |
| ヤマザキ コウスケ 山﨑 晧亮 (循環器内科医師) |
| 招聘医師 | ||
|---|---|---|
| 全 完 (ゼン カン) | 循環器内科 | |