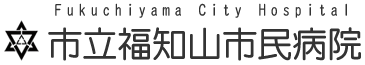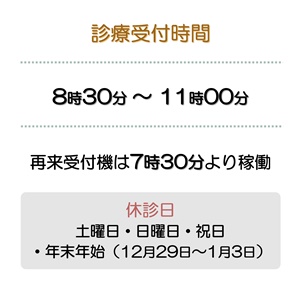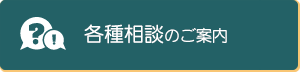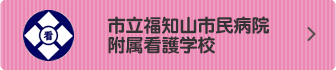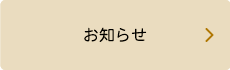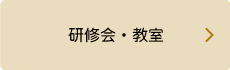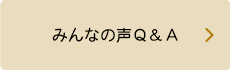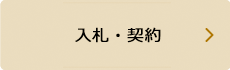本文
糖尿病内科
*知りたい内容をクリックしてください。
特色 / 診療内容 / 学会学術活動 / 週間診療予定表 / 担当医師
特色
糖尿病・生活習慣病の治療には患者さんと(ご家族や友人)、医師・医療スタッフが一緒にチームとなって診ていくことが大切です。まずは糖尿病について知ることから始まり、チームで出来ることを見つけながら治療を進めます。糖尿病の初期は症状が少ないため、治療を中断される方がいますが、その間も徐々に病態は進行し危険な状態になることもあります。初期に限らず糖尿病治療をされている方が治療中断することがないようにサポートします、糖尿病に対しての思いのみならず、医療費の問題、通院の問題、時には家族の問題など患者さんが困っていることにも可能な限り対応します。数値で診ることの多い科ですが、数値では表せない部分・数値に表れない部分も多い科です、抱え込まずに声を聞かせてください。
診療内容
糖尿病について
膵臓のβ細胞で作られるインスリンには種々の作用があり、その中で血糖値を下げる作用が特に有名です。糖尿病とは、インスリンの作用不足により慢性的に高血糖状態を主徴とする疾患です。
糖尿病は,次の4つに大きく分けられます。
- 1型糖尿病
自己免疫的又は特発的なβ細胞の破壊・消失で、通常はインスリンが欠乏する病態になります。 - 2型糖尿病
インスリン分泌低下を主体とするものと、インスリン抵抗性(効きの悪さ)を主体とするものとが組み合わさり、相対的にインスリン作用が不足する病態です。 - その他の糖尿病
遺伝的、膵臓・肝臓の病気、薬剤によるものなどがあります。 - 妊娠糖尿病
妊娠中に発症した糖代謝異常です。
(全て対応できますが、病態によっては大学などの医療機関と連携して診療します。)
患者さん個人の状態をしっかりと見極めて、生活の見直しを行うことと、インスリン分泌の能力や、インスリン抵抗性を評価して適切に治療にあたることが大切です。
糖尿病専門外来では医師の診療だけではなく、栄養指導や看護師、糖尿病療養指導士による指導も適切行っています。合併症の予防・治療にも積極的に取り組み、各専門科との連携も行っています。糖尿病腎症や足病変に対しては専門の外来もあります。
糖尿病専門外来で主に診ている項目
生活・食事療法・運動療法
患者さん個人に合わせた食事内容、運動量を設定します。続けていくことが今後の健康に大きくかかわってきます。まずは続けていけそうなレベルを話し合って決め、さらにステップアップできるよう支援します。
体重、体組成(筋肉量、脂肪量、骨量など)
標準体重(kg)は、身長(m)×身長(m)×22で計算できます。これを基準に個人に合わせた目標体重を決めます。肥満の改善によってインスリンが効きやすい状態へと戻ること、動脈硬化や血圧、脂質にもよい効果が期待でき、腎臓への負担も軽減されます。また、筋肉をつけることは血糖の改善のみならず、筋萎縮(サルコペニア)による生活の質の低下を予防します。
血糖値、血糖変動
高血糖によって引き起こされる様々な合併症の予防に必要です。まずは食事療法・運動療法を基本とします。それでも不十分な場合は内服薬や、Glp-1注射剤、インスリン注射剤などを使用して血糖を安定させます。注射の導入は、入院せずに外来で行うことも可能です。最近は低血糖も様々な病気の原因となり得ると分かってきました。低血糖なく血糖を安定させることを目指します。
高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症(痛風)など
心臓血管や脳血管など動脈硬化病変に関連します。糖尿病同様に悪化には注意が必要です。
糖尿病に関する合併症
神経障害
両手両足の感覚低下、痺れ、痛みが有名ですが、立ちくらみや、頑固な便秘・下痢、勃起障害などもあります。
網膜症
目の病変で、進行すると失明の原因になります。末期になるまで自覚症状が分かりにくいため症状がなくても定期的に眼科受診してチェックを受けることが必要です。
腎症
高血糖や高血圧などは糖尿病腎症の進行を早めます。人工透析になった原因の4割強が糖尿病腎症です。早期からチェックと対策を行っています。肥満の対策も腎臓病には重要となります。
動脈硬化(脳動脈、心血管、下肢動脈)
血糖、血圧、脂質、尿酸、体重管理などはもちろんのこと、禁煙が必要です。
足病変
血流の低下に加えて、視力の低下、感覚の低下などのため起こりやすく気づきにくい状態の可能性があります。外来でもチェックしますが、自分の足を観察する(してもらう)習慣が必要です。
歯科連携
以前より糖尿病と歯周病の関連が指摘されていました。その他、食事療法にもよく噛むことが必要であり、歯科でのチェック・治療は糖尿病管理に有効と考えています。
認知症・サルコペニア・骨粗鬆症・感染症など
糖尿病の方では起こりやすいことが分かっています。特に血糖コントロールが不十分な方では感染症が重症化しやすく注意が必要です。
健診・がん検診の利用の推進
糖尿病専門外来ではカバー出来ない部分があります。かかりつけ医の受診や、健診、がん検診などの利用を合わせて健康を管理することが必要です。
外来業務
糖尿病専門外来を、月曜日~金曜日まで毎日行っています。予約外来が主となりますが、紹介や救急疾患への対応も可能です。
多くは2型糖尿病ですが、1型糖尿病、妊娠糖尿病、糖尿病合併妊娠、その他の糖尿病に対しても専門的な治療を行っています。(当院はインスリンポンプ、持続グルコース測定器の取扱い医療機関です)
教育入院
外来診療のみでは糖尿病の改善が難しい方や、糖尿病は安定しているものの療養が必要と考えられる方に糖尿病教育入院を行っています。教育入院は約2週間を基本としていますが、程度や経過により調整は可能です。食事療法の見直しなどを数日~1週間程度で行う短期の教育入院も行っています。
急性期合併症
救急疾患(高血糖、低血糖など)への対応も総合内科や地域救命救急センターと連携して治療を行います。
併診
他科入院中の糖尿病患者さんに対しては血糖管理の他に、できるかぎり糖尿病を知ってもらうべく療養面でのサポートを行っています。
啓発活動
当院の糖尿病チームと協力して、糖尿病教室を定期的に行っています。糖尿病患者さんのみではなく、糖尿病に興味があればどなたでも参加可能です。また、11月14日の世界糖尿病デーに近い日程で糖尿病のイベントを行っています。
学会学術活動
日本糖尿病学会、日本内科学会
担当医師
| ミツハシ カヅテル 三橋 一輝 (糖尿病内科医長) |
最終学歴 | 京都府立医科大学 平成17年卒業 京都府立医科大学大学院 平成28年単位修得 |
|---|---|---|
| 学位 | 医学博士 | |
| 専門分野 | 糖尿病 | |
| 専門医・認定医等 | 日本糖尿病学会専門医・研修指導医 日本内科学会総合内科専門医 京都府立医科大学臨床准教授 |
|
| 診療についてのモットー | 数年先から数十年先を考え患者さんと一緒に治療に取り組みます。 | |
| コバヤシ アヤカ 小林 彩花 (糖尿病内科医師) |
最終学歴 | 滋賀医科大学 平成26年卒業 京都府立医科大学大学院 令和6年修了 |
| 学位 | 医学博士 | |
| 専門分野 | 糖尿病、内分泌 | |
| 専門医・認定医等 | 日本糖尿病学会専門医 日本内科学会認定内科医 |
|
| 診療についてのモットー | 患者様の心情によりそった診療を心がけています。 | |
| トクダ アヤカ 德田 彩加 (糖尿病内科医師) |
最終学歴 | 宮崎大学 平成31年卒業 |
| 専門分野 | 糖尿病、内分泌 | |
| 診療についてのモットー | 丁寧なコミュニケーションから見えてくるものを大切に。 患者さん一人一人に寄り添い、治療の選択肢をより多く提示できるようにしていきたいです。 |
| 招聘医師 | ||
|---|---|---|
| 阪井 貴美子(サカイ キミコ) | 糖尿病、内分泌 | |