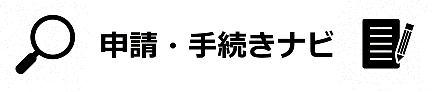ワード
新文化ホール マイナンバーカード ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
後期高齢者医療制度
|
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひマイナ保険証をご利用ください。 ※長期入院該当については引続き届出が必要となります。 詳しくは下記をご覧ください。 厚労省 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク> |
概要
- 75歳以上の人及び65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で京都府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人が対象となる医療保険制度です。
- 後期高齢者医療制度は、京都府内の全市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。
- 京都府後期高齢者医療広域連合は、保険料の決定・財政運営・被保険者の認定・医療を受けたときの給付・健康診査事業を行う市町村への補助などを行います。
- 福知山市は、保険料の収納・被保険者からの申請や届出の受付・資格確認書の引き渡し・健康診査事業の実施などを行います。
制度の詳細については京都府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
京都府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
被保険者
75歳以上の人(誕生日の当日から)と65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で申請により京都府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人が被保険者となります。
後期高齢者医療資格確認書と給付
令和6年12月2日から、被保険者証の新規発行は廃止となり、後期高齢者医療制度に加入する人には、1人に1枚「資格確認書」を交付しています。
なお、この取扱いは令和8年7月末までの暫定的な取扱いとなります。
医療機関を受診されるときや、医師の指示で訪問看護を受けるときは必ず資格確認書またはマイナ保険証を医療機関等に提示してください。
医療費の自己負担
病気やけがで医療機関を受診したときは、医療費の1割、2割または3割が自己負担となります。
自己負担の割合は、世帯の所得や収入によって異なります。
| 所得区分 | 自己負担の割合 | |
| 現役並み所得者 | 同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 | 3割負担 |
| 一般2 | 同じ世帯に一人でも住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる、かつ被保険者が1人の場合「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上)の人 | 2割負担 |
| 一般1 | 「現役並み所得者」「一般2」「低所得2」「低所得1」以外の人 | 1割負担 |
| 低所得2 | 世帯全員が住民税非課税の人 | |
| 低所得1 | 世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)が0円となる人または老齢福祉年金を受給している人 | |
基準収入額適用申請
住民税課税所得が145万円以上の人は「現役並み所得者」3割負担と判定されますが、収入が次のいずれかの基準に該当する場合は2割負担または1割負担となりますので、市役所保険年金課でお手続きください。
| 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 | 被保険者の収入額が383万円未満 |
| 同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合 | 被保険者全員の収入額合計が520万円未満 |
|
同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、その収入が383万円以上であっても、70歳以上75歳未満の人がいる場合 |
被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の収入額合計が520万円未満 |
限度額適用・標準負担額の減額
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額認定証」の新規発行は廃止となりました。
今後は資格確認書に限度額等の適用区分を記載します。限度額等の適用区分の記載については、申請が必要ですので、現在記載がない人でご希望される人は、保険年金課または各支所窓口相談係にて申請してください。
※マイナ保険証を利用される場合は、申請不要です。
葬祭費
被保険者が亡くなられたとき、2年以内に申請することにより喪主様に50,000円が支給されます。
保険料
保険料は、均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額で被保険者一人ひとりに賦課されます。
保険料の計算方法
[令和7年度]
京都府の保険料(限度額80万円)=均等割額(被保険者一人あたり) 56,340円+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×10.95%
所得の低い人の軽減
<均等割額の軽減>
所得の低い人は世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
保険料のお支払方法
対象となる年金額が年額18万円以上の人は原則、年金から保険料をお支払いただきます。(特別徴収)
※介護保険料と合わせた保険料額が対象となる年金額の2分の1を超える場合は口座振替または納付書等でお支払いただきます。
それ以外の人は、口座振替・納付書等でお支払いただきます。(普通徴収)
| 期 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |
| 納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
| 納期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
普通徴収の人は、便利な口座振替をぜひご利用ください。
【手続きに必要な持ち物】
(1)市役所保険年金課または各支所窓口相談係で手続きする場合
・本人確認書類
・キャッシュカード(暗証番号の入力があります)
(2)市内の指定金融機関で手続きする場合
・預金通帳
・通帳届出印
|
京都銀行 京都北都信用金庫 京都丹の国農業協同組合 京都農業協同組合 近畿労働金庫 但馬銀行* 但馬信用金庫* 中兵庫信用金庫 ゆうちょ銀行 *市役所・各支所での手続きはできません。 |
届出に必要なもの
後期高齢者医療制度の申請や届出をしていただくときには次の書類の提示が必要です。
| 被保険者本人が手続をされるとき |
申請書(窓口に備え付けあり) 後期高齢者医療資格確認書(資格情報のお知らせ)再交付申請書 [PDFファイル/79KB] マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書) 顔写真つきの本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
| 代理人が手続をされるとき |
上記申請書 本人からの委任状(任意様式可) 委任状 [PDFファイル/94KB] 本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書) 代理人の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
|
葬祭費申請書(窓口に備え付けあり) 会葬礼状または葬儀費用の領収書 確認書類がない場合 葬祭執行申立書 [PDFファイル/87KB] 喪主様の振込先口座が確認できるもの |
|
相続代表届(窓口に備え付けあり) |
|
転居届(窓口備え付け) |
|
転出届(窓口備え付け) 後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(窓口備え付け) ※発行した後期高齢者医療負担区分等証明書は転出先の市区町村後期高齢者医療保険担当窓口で提出する必要があります。 |
|
転入届(窓口備え付け) 転出元の市区町村で発行された後期高齢者医療負担区分等証明書をお持ちください。 |
| 限度区分併記申請 | 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/95KB] |
| 後期高齢者医療高額療養費支給申請 | 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/131KB] |
| 療養費支給申請 | 療養費支給申請書 [PDFファイル/177KB] |
| 長期入院申請 | 後期高齢者医療入院日数届書 [PDFファイル/96KB] |
| 特定疾病療養受療証申請書 | 後期高齢者医療特定疾病認定申請書 [PDFファイル/133KB] |
| 被保険者本人が手続をされるとき |
資格確認書 マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書) 本人確認書類(次の1か2のうちいずれか) 1 顔写真つきの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 2 顔写真なしの証明書2種類以上(資格確認書・介護保険者証・年金手帳・年金証書など) |
| 代理人が手続をされるとき |
本人の資格確認書または本人からの委任状(任意様式可) 本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知書) 代理人の本人確認書類(次の1か2のうちいずれか) 1 顔写真つきの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 2 顔写真なしの証明書2種類以上(資格確認書・介護保険証・年金手帳・年金証書など) |
※後期高齢者医療制度にかかる届出は市役所1階20番保険年金課または各支所窓口相談係までお越しください。
第三者行為の届出
交通事故や犯罪・食中毒等の被害者となった場合は、加害者が過失割合に応じて医療費を負担(賠償)する必要があります。いったん後期高齢者医療制度で診療を受けた場合は、あとで後期高齢者医療制度から加害者に医療費を請求しますので、必ず市役所保険年金課に届け出てください。
必要な書類
詳細については京都府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
京都府後期高齢者医療広域連合 第三者行為<外部リンク>
※福祉医療費助成事業または重度心身障害老人健康管理事業の受給中の人は次の書類の提出が必要になります。
第三者行為損害賠償に係る「福祉医療助成事業」・「市町村重度心身障害老人健康管理事業」委任状兼同意書 様式16 [PDFファイル/125KB]
※指定公費負担医療の受給中の人は次の書類の提出が必要になります。
第三者行為損害賠償に係る「指定公費負担医療」委任状兼同意書 様式16-2 [PDFファイル/124KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)